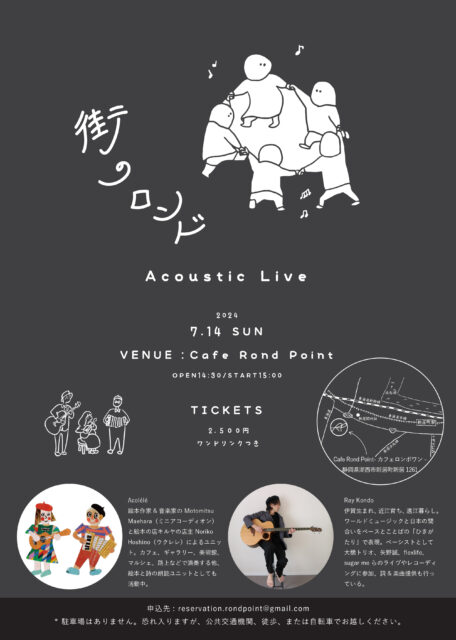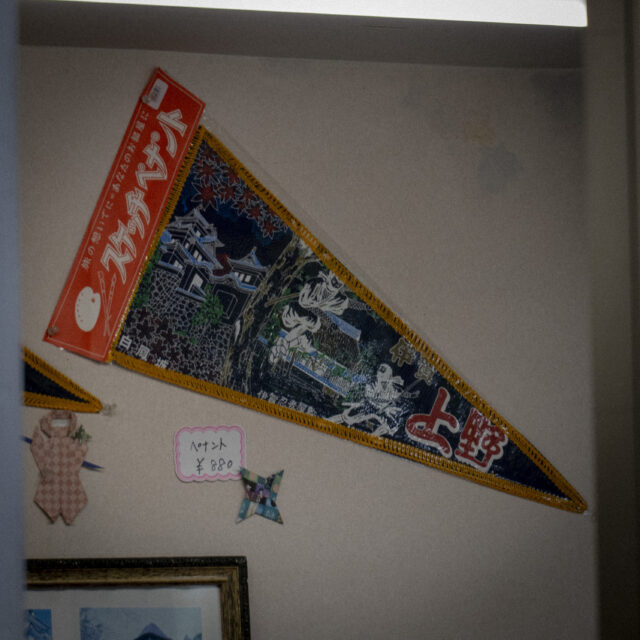豊橋市にある「水上ビル」。
戦後の闇市をルーツに、農業用水路の上にビルを建てた、という奇想天外な商店街。
これぞレトロ! という、豊橋ならではの界隈です。
老朽化や耐震基準などから、もう余命が約二十年、と宣言しちゃってるのですが、
それでも近年、若者からいいおっちゃんまで、人々が集い、ええ味出してます。
さて、僕はまだ、昨年この場所を知ったばかりで、
その後も訪れた日がお目当ての店の定休日だったり、なんやかやでニアミスばかりしてて
まだホームというよりは半分アウェイなのですが
なんと、今年は「夏至まつり」に出演させてもらうことになりました。
しかも、夏至と梅雨がちょうど重なることから、最初から開き直って
「あめのひ音楽会」
…これはやられましたね。雨天結構、というコンセプトの清々しさに、すっかり参りました。
で、のほほんと構えていたのだけど、開催の一週間前ぐらいになって、ふと気づく。
野外ステージ2本。よく考えたら自分が濡れるのを我慢すればいいだけじゃなくて、楽器や機材も濡れるじゃないか。
残念ながら僕のベースという楽器は、アコースティックだけど広場で生音で演奏するには音が小さく、足元にケーブルとか切り替えとか、電気の機材が必要なのだ。なにげに配線もややこしい。雨が降ったらずらかる、なんてこともまぁまぁ無理。
木の楽器も、できれば濡らしたくないし、その日以降雨が続くっぽいから、乾かすこともできない。
それでにわかに焦り出し、機材を床から上げられないか主催者さんと相談しつつ、楽器や構成を変えようとか、もじゃもじゃといじりだし、当日が迫ってきました。
僕のタイムテーブルでは降雨か微妙なとこで、なんとかなるかなと思ったのだけど、
全体のことも考えてでしょう、前日になって野外ステージは中止になり、かわりに美容室 “Pokkecise” さんの店先での演奏、ということに変わりました。
ポッケチセさんならアットホームだし安心だ。音もそんなにでかくなくていい。
でも、20分 x 2 で考えてたセットリスト、30分 x 1 に変えられるか??
何事も臨機応変さがない僕はまた大慌て。いろいろ試行錯誤した結果。
「どうしても決められないとこはお客さんに聞いてみよう」
さて当日。
幸いまだ雨はなく、駐車場から現地へ。
会場予定だった EM キャンパスの広場には結構人がいて、その向こうのポッケチセにも人がいて。
メタバースも感じながら、ちょっとイメトレして、サウンドチェックして、本番に臨んだのでした。
この日のセットは先日から気に入っている新曲「アフロアルバ」を冒頭に、
その後はガラッと変えました。
長いこと寝かせてたダブルベース、ようやく起こして、全8曲のうち3曲。
それから完全な新曲を3曲。といってもこの日をテーマに作ったので、今後やるかはわかりませんが。
「ホームタウン」7拍子のジャズブルース
「あめのひ商店街レゲエ」地表におちる雨粒のためのダブ
「げっしのひ」働くおじさんと齧歯類のためのロックンロール
他にも、この日が誕生日の Green Gartside に捧げて、あるモノを用意してたんだけど、時間が足りず封印。
しかし…楽しかったー。
お客さんはどう贔屓目に見ても少なく、中止された第二会場の出番を待って見逃した人もいたし、そもそも気づかなかったり、観た結果素通りする人も多かったし、その一方でめちゃめちゃガン観、がん聴きしてくれる人もいたので… that’s musician’s life です。
中でも、音楽家同士とはいえ、次が出番のハヤシハンドパンさんがとても気に入ってくださって、その後いろいろ話して盛り上がり、即席のジャムをすることになりました。

昔は気軽にインプロ、飛び入りしてたんだけど、なんか懐かしい。
しかもこちらのステージは、生音にかるくオフマイクだけ取ってもらったから、一番やりやすいし心地いいシチュエーションですよね。
ハンドパンの音色は、ハヤシさんの音楽性や技量もあってすばらしく、
音量が小さいのに、というか小さいがこそ、人々の耳をひきつけてました。
たくさんの人が聴き入ってて、そこに混じれてよかったです。
ライヴでもジャムでもそうなんだけど、予定調和じゃないことが起こると、そのあとの余韻が面白くて、この日もしばらくの間、なんだかんだ浸ってました。
「ホームタウン」っていうのは、タイトルからして白状してますが、
チャボさんの『絵』の冒頭曲のオマージュです。
だいぶ違う音楽に聴こえるだろうけど。
もし、野外ステージでやれることあったら、またやってみよう。
アルバムに入れるかは、どうするかな?
超意外なことに、僕の音楽や声はさるメジャーな方の、メジャーじゃない音楽に似てる、と感想もらいました。
好きな三重のカフェの旦那さんも、最初にお会いしたときにそう仰ってたので。あながちホラや社交辞令でもないのでしょう。
これまでほっとんど聴いたことのない人で、改めて聴いてみても、ますます遠いなと思うだけで、ほとんど共通点は感じられない。
かっこいいけど。
でも、また聴いてみようかな。
自分だけじゃわからないから、音楽って面白いですよね。