今年も折り返した。
7.1 がそうなんだろうけど、7.7 ってことにする。
2年前か3年前か、river silver [side a] を出した。
river silver = 銀河
なのでそうした。7.7がゾロ目ってだけじゃなくて、後からいいこじつけがみつかったわけだ。
何を隠そう、そのアルバムは今絶賛廃盤中だ。[side b] 合わせて、合計16曲。
中には我ながら、「めいさく」もいくつかある。
grace behind the word や みつかったぞ や ホタル や。
[side b] には double time runes がある。


CD やアナログと違って小回りのきく配信リリースとはいえ、はっきり書くが、ぜんっぜん採算に合わないのだ。儲かるどころの話じゃないって話。
こんなんじゃ、ゲストミュージシャンやイラストレーターに頼むなんて無理の無理。ちゃんとギャラ払いたいからね。レーベルオーナーとして。いや、人として。
配信ってなんなんだろう、とは常に思う。Apple はじめ、彼らのやりかたって、かなり疑問も感じてる。「1984」じゃない、って IBM を打ち砕くイメージで登場した Mac、実はビッグブラザーでしょ?
と、僕は Mac に向かって入力してる。その先は巨大サーバー。ビッグブラザーじゃん。
いろんな人巻き込んで、お金かけて、宣伝して、しまくって、広がって、元が取れる。
それは一つの有効なやり方だろう。資本主義。まだ王道なのかもしれない。この世の会員。
それができるのは、まず才能のある人だと思う。それは素晴らしいことだ。
音楽の才能。マーケティングの才能。人間としての魅力。言うまでもないので言わない。みんなわかってますよね。
なら、僕みたいに少なくとも、自分の得意なこと、より、自分のやりたいこと、を優先する人(≒偏屈な人)にとってはどうすればよいのだろう。
むずいね、無理だね、あきらめな、絶望だね、そんなことないね、どうでもいいね、最高だな、やばいな、ほなほんでええやんけ。いやいや、無意味なことなんてこの世にないやろ。
まぁそんな感じだ。あらゆる葛藤を360度 x 3600回超えて、僕も誰かも、こうやってオンラインリリースをしてる。「いいね」ごときでカウントできないっしょ。
それに比べたらアーティストイメージなんて関係ないし、ほんと、どうでもいいのだ。それに、やがて、人は灰になるし、チリになる。肺が使えなくもなる。
サーバーにデータすら残らない。何万字になっても数KB。解像度が高くても最適化すれば誤消去。諸行無常。
さて、全く重要じゃない前置きは終わり。
ともあれ、river silver は僕の(ほぼ)代表作でもある。Voice of Marble と別の意味で、問題大アリのかけがえの少ない作品集だ。

これは、改めてリリースしたい。できれば一年単位でなく、死後だって残したいものだ。
…間に合わなかった。いや、生きてるが。7.7 に。
数曲、リメイクしたいと思ったんだけど、この状況じゃなー。
だが、必ず、今年中には再リリースしたい、と思っています。
なんでこんな前振りが必要だったんだろう。
7.7 ということでこれは外せなかったのだ。あの前夜は赤い靴のライヴを 7th floor でしていて、仲間も沢山いた。
その同じ時、西日本では集中豪雨だった。
同じような状況だ。思い出さずにはいられない。
どうかご無事で、九州の方々。
同じような状況 ー もっと悪くなってないだろうか。香港、東京。アメリカ。目で確かめることも、容易ではない。そうなるとメディアを介したものしか、「社会」として認識できない。
これはもともとそうだったか。「社会」は最初教科書で、次に新聞やテレビで、それからもずっとそうで、町内会や自治会や、業界や、が入ってくるとしても、SNS やスマホで、でまたメディアになってしまう。
そうなると、リアルとメディアの関係は、永遠に。
折り返し。
また今年も何か、無茶なことをしよう、と思ってはじめた
moon x moon
完全に自己満足が発端なのだけど、ギリ続いている。
あと11曲の予定。
僕は昔から、曲の断片は溜めてきたから、作りかけ含めると1,000曲ぐらいのアイデアはあるのだけど、いかんせん歌詞が書けないのと、歌の才能が全くないので、ほとんど断念してきた。
もともと日本語の歌詞など興味はなく、インストか洋楽しか聴けなかった。
RC の「シングル・マン」を聴いてからだ。詞ってすごい、と思ったのは。
それからも随分経って、ようやく言葉が何処かを通って出るようになってきた。
才能がないなりに、少しは自分の声が出るようにもなってきた。
そんな遠回りをせずに、提供したり、共作したり、フィーチャリングボーカル使えばいいじゃん、って人は思うでしょう。
そんな単純じゃない。
フィーチャリングボーカルなんて、やっていいのは大沢伸一までだと僕は思ってるし。
自分も最高のシンガーとバンドをやったし、ものすごく素晴らしいボーカリストとも、たいがい共演した、それを経ての実感だ。
「うたうひとは、自分の世界を、うたいたい」。その方が輝く。
それに、僕は人を「使う」という感覚に、馴染めない。
プロデューサーっていうのが苦手なのだ。
ある意味対等でありつつ、意思を尊重して何かを見出すってのは、本当に難しいことだ。でもここからしか、長く聴けるマジックは生まれない、と思ってる。これは滅多にないこと。
それでも、僕のヘンテコな歌詞を歌ってくれたり、イメージをわかってくれる人なら、機会があれば共演したいものです。またそれが、人を介して、または独力で、きちんと仕事になるのならば、よいと思う。時間的なことを含めて。
やっぱりアイデアがある以上、人にお願いするにしても、自分である程度わかった上で、と思います。
しかし、わからない部分こそが、重要だったりもする。
難しい。ですよ。
難しいから、ガタガタ言わずに、やるんだ。
moon x moon は、リリース日以外にルールを決めていない、シングルリリースプロジェクトです。
昔から曲のアイデアはあるので、そこに、漸く詞がついたものを形にしたり、ということだったり。
とはいえ、ときには20年も前にアイデアが訪れたものを一度も人に聴かせずに、「新しく」出す、なんて馬鹿な奴も、そんなにいないと思います。そんな要領悪い人、いるの? ていうか詐欺? 案外いっぱいいる?
この24曲 25曲 の中から、残っていく曲も、発展させるのも、1年後にあっさり消し去ってしまうものも、ありそうです。
まぁそれでも、振り返ってみます。どれも、作った時は夢中でやってるから。
最高だと信じて、ね。
僕のリスナーは、少ないです。稀少な金属(レイア・メタル)です、あなたは。
が、はまるとハマるらしく、熱心に聴いてくれたり、するようです。
本当ありがとう!
僕は特にターゲットを決めたりしていないし、そもそも作品に表面的な一貫性はほとんどないので、もっと意外なとこから聴いてくれたりもするのかな、とは思ってます。
自分でもいいな、と思うのと、割と人気が一致するのが
Atto Iu Ma Ni
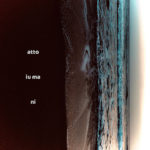
この曲、構成もうちょっと伸ばしたかったり、最後に歌やソロを加えたかったり、もします。
まずはライヴで育っていく曲、と思ったんだけど、この状況だからね…
後悔としては、タイトルは本来は “a tto iu ma ni” でした。こうできなかったのは、業者の Cap & Low(大文字小文字ルール)制限。”A Tto Iu Ma Ni” だとバランスが悪い。全部小文字にできるハックがあると、だいぶ後に知る。
「くつがえる ときのいわ」というのは「さざれ石」のことです。恐らく。
自分ではとても思い入れがあって、気に入ってたけどリリース後に聴き返せなくなってしまった曲もあって、その中で割と人気があるのが
わらい x きみ

です。これ、曲や詞としてはほんと大切なんだな。ボーカルでかすぎるね。
ジャケットは、京都在住の素晴らしい SSW、隆太くんによるものです。
自分では最高に気に入っていて、リリース後のトラブルもあり殆ど告知もしていないけど、いつの間にかよく聴いてもらえてるのが
Yesterday Morning

最近ようやく、リアルタイム歌詞も表示されるようになったので、きいて、よんでみてください。反省としてはコーラスがデカすぎるのですが、アウトロなんかはとてもご満悦です。
これはライヴでの再現はハナから求めていなくて、アコースティックで全く別物として成立します。だから楽しみでもある。
カーステで聴くとすごくよくて、割と人からも好意見もらえてるのが
Different Town

やっぱ8弦ベースがいいんですよね。
ジャケは、尾道で買ったミニカー。
地味だけど安定して聴かれてるのが
Waltz for July
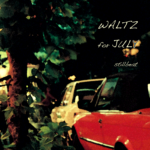
です。本来は今月にリ・リリースするべきだった曲。待ちきれず1月に出してごめんなさい。やっぱインストゥルメンタルはいいんでしょうね。
ジャケットは、90年代の京都のさる風景です。
それから、よく聴いてもらえて、いいコメントももらえたのが
あかりをつけたら

これは死ぬ前には出さなきゃ(リリース=解放しなきゃ)、と思ってた曲。2バージョンあるけど、こちらがオリジナルアレンジ。とはいえ、ボーカルや、ドラムのマイキングに、今ならもっとこうしたい、というのはありますが。
自分の形はできたので。やや解放できてきた。だろうか。
至って健康ですよ。ただこの時世何があっても、との心境なのです。ジャケは近江大津のお宿です。
ほぼスルーされてる曲もいっぱいありまして、んなもん書くなよってことだけど
So It’ll Be

はもったいないですね。やっぱAメロのレンジが低すぎたのでしょう。歌詞含めて冒険心富んでるのになぁ。
Lou Reed も、磁石の武者、クシャナ殿下も、涙ぐんでる。
この「ペンシルドラム」の味も、捨てがたいのです。これはものすごく簡単なドラムセットで、マイクの前に立ててるポップガードっていう黒い金魚すくいみたいな物体の、ストッキング部分と縁の部分を、鉛筆で叩いたものなのだ。ASMR を先取りしてた。ジャケットは、エフェクトボードの光です。
それから、リリース後にものすごく再生されたと思ったら、いつのまにかその記録がなくなってしまっているのが
rivet

なんだったんだろう? いろんな意味で、重要な作品。好き嫌いはあるでしょうけれど。
タイトルが、右中央に浮かび上がっているのがおわかりでしょうか。
もう一つ、ほぼ完全にスルーされているのが
Black & White River

メロウなのが裏目に出たのか。あと、ジャケットが棺桶みたいで伝わらなかったのか。伝わったからなのかな?
愛しの目黒川。こないだ久しぶりに歩いたら、大橋ジャンクションはツタが絡んでて甲子園のよう。ポリドールの面影もなく。ただ、あの夜無数に星があった氷川橋の路面はそのままでした。
完全に太陽系外なのが
neptune

ま、そういう歌詞、もとい、詩なんだけどね。
中央からや権威から離れて、人間が作った歴史からも、っていう。
この曲のジャケットは4パターンあって、一番、おっと思うのを選んだのですが、
他のは美しすぎた。最後まで迷って、寂しげだけど何か言いたそうなこれにした。
でも全て気に入ってて、それらはまた公開するかもしれません。
そして、とても反応がよいのが
あめがおおきくゆらいだサイン

これは、ほんとになんのことかさっぱりわからないんだけど
なにか、いいんです。
さいごに
よこくの太陽 <feat. 神谷>

洵平くんやってくれましたね。当初かなり聴いてもらえました。
まぁ客観的に、よいのかというと…わからない 笑
以降、順当に、聴かれなくなっていますが。
それからこのジャケは、吉祥寺シアターという所の壁の一部を基にしています。
さて、そんなこんなもありつつ、これからも進むのだ。
七夕に彦星と織姫は会えるのか。
最もポップな、Z-A の運命やいかに。
<おことわり>
* 適宜、この投稿は増改築しています。ものすごく雑に書き始めたけれども、重要なことをたくさん含んでいるので。
* 数え直すと、なんと10月は2回も満月来るんですね。1曲増えたぜ…



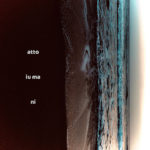



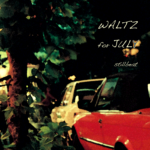












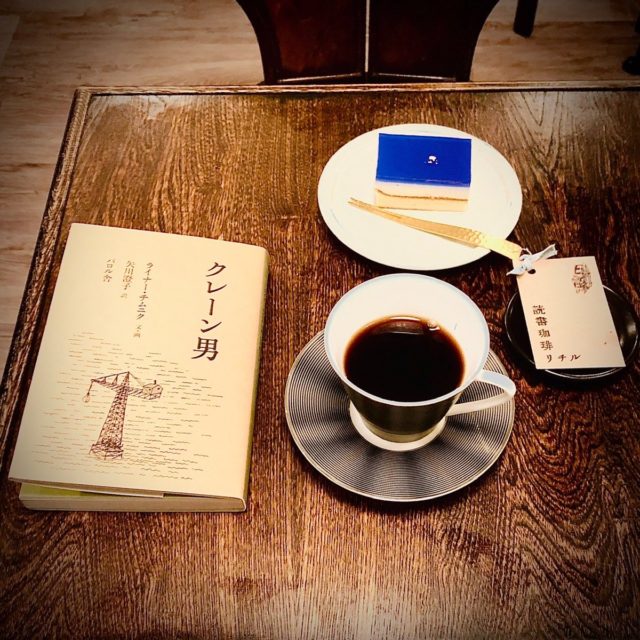





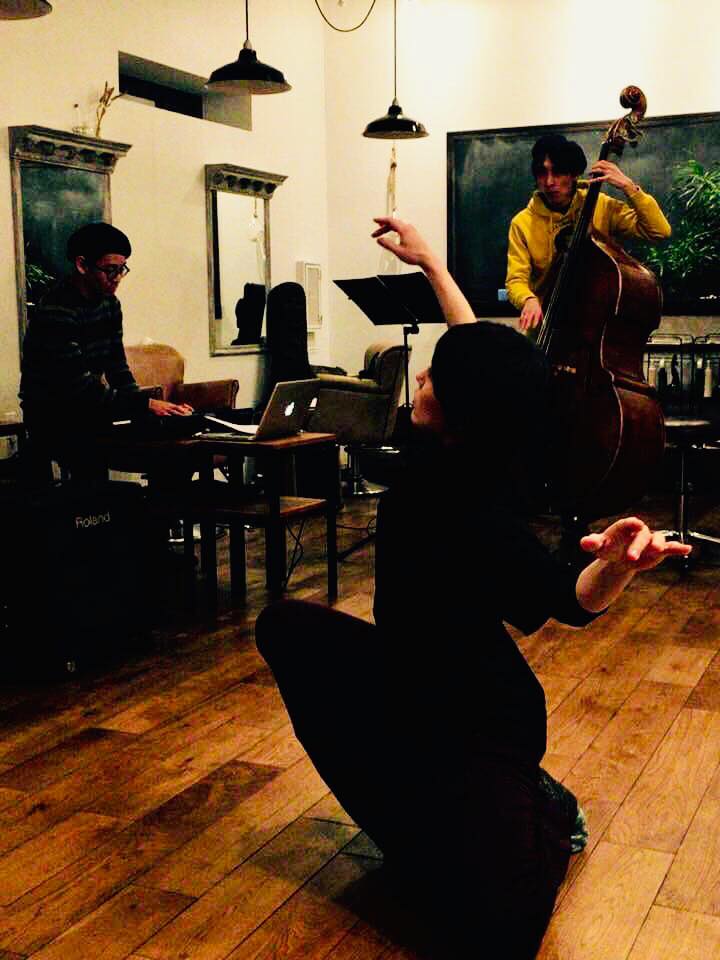
 パリ在住、日本と往復して活動する moto 君とは久々の共演。DJ でもあり、近年は独創的な絵本やコラージュアート、Little Creatures のアルバムジャケットなどでも活躍する才能の塊です。みきさんは先日初めてお会いしたのですが、かっこよくて。
パリ在住、日本と往復して活動する moto 君とは久々の共演。DJ でもあり、近年は独創的な絵本やコラージュアート、Little Creatures のアルバムジャケットなどでも活躍する才能の塊です。みきさんは先日初めてお会いしたのですが、かっこよくて。