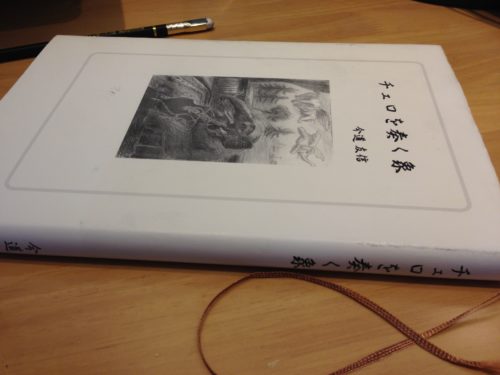世界は王国だけじゃない
王様がいる世界なんてお伽噺だけのこと
…でもないけれども
少なくともこの国には王様はいない
いや、随分長いこと、日本に「王」は居なかった気がするのだが
額田王とか、そういう
…
ちがうか
しかしなんで、日本語を話すぼくらでもこれほど「王」という言葉が身近なのだ
…
世界は王を求めているのだろうか?
宮崎駿の「風立ちぬ」はまだ観ていないけれども
彼の作品は大人になって、いろいろな見方が出来ると判ってから
好きになった
子供の頃は「カリオストロの城」ぐらいしかピンと来なかった
「風の谷のナウシカ」は惹かれたけれども意味が分からなかった
他は、画がかわいすぎたのか、ヒットしすぎてたのか、敬遠した
今では、原画スタッフで関わった「空飛ぶゆうれい船」から
「未来少年コナン」からルパンの「死の翼アルバトロス」にしても
「ハウルの動く城」にしてもとても深いものだとわかるけれども(遅いか)
しかし中でも一番強烈なのが漫画版の「ナウシカ」で
この後半部の展開は現在露わになりつつある実世界の枠組みに
恐ろしいほどに迫っていると思う
そこでは幾人かの「王」が登場する
森の人の王、エフタルの王、トルメキアの王、土鬼の王
そして蟲の王
無垢を意味する巨神兵の「オーマ」も(「オーム」との類音だけでなしに)
王を想起させる
まぁ、なんで宮崎作品では重要な配役がことごとく王子や王女ばかりなのかと
そういう疑問もあるのだ
民衆の殆どは、王家ではないのに… なんして、これで支持を集めてるの? ってやつだ
おれらって、届かない権力者に憧れて、結局支持するの?
みたいな
ともあれ
彼ら、彼女らは「誇り高い」とされる
「誇り高き」「気高き」という形容詞が、たとえ争う敵同士であっても共振させ
結びつけるという鍵にはなっているようだ
ふぅん
たぶん
それには同意なので
無理矢理理由の一つを掘り出せば
おれらって、自分の王であるべきなんだよな
現実の身分に関わらず
…ってことなんかな
与えられた生を最大限に全うする
それって多分、自分に対する王道なんだろうな
と思う
社会的には「誇り」って何かという大きなトラップがあって
だったら軍事力を増強すればいいのか、だったら周りをサゲればいいのか
カネ撒いて嘘をついて目隠しイベント呼べばいいのかとなりがちだけれども
ボロボロの中でも誇りを持つ
時にはボロをさらけ出すことが
実は誇りなんじゃないかなと
そんなこと思う
2013のあきである