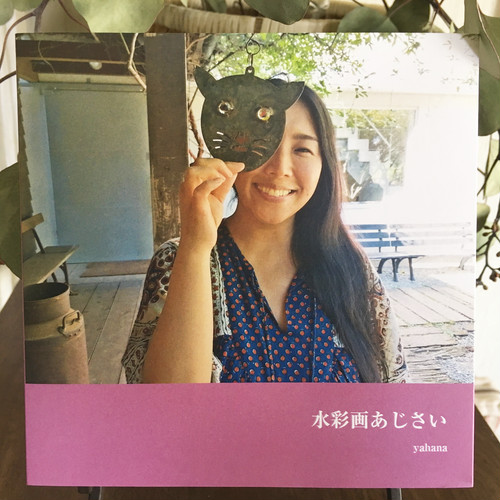ホールはひろい の続きである。
1.29にNHK大阪ホールで演奏していた内容は収録されていて、配信される。
前回11.19、東京での公演も収録され、こちらは先に確認に観せてもらった。
とてもいいコンサートだったな、と改めて思いつつ – 自分の痩せっぷりには改めてびびったが – 次のアルバムに入るようですよ。
今回は、また違う感じのコンサートになったかな。
– と書いているうちに、実はもう配信されていて、本日いっぱいまでアーカイブです。
トリオどんの唄が素晴らしいですよ。僕は髪がだいぶ伸びて、見た目はこっちの方がサマになってたかな。
舞台は深い。そこに辿り着く多くのもの。
例えばこれを車の部品と完成形に見ることもできるだろう。
さまざまな商品の発表会に投影することもできるだろう。
だが、少し違う。いやだいぶ、違う。
演奏舞台はシステマティックにもできるが、それだけなら全部同期にすればいい。
口パクでもメロダインでもホログラフィでも VR でもなんでも使えばいい。
しかし、人間がやることとテクノロジー、決まりごとと決まってないことが同居する舞台。
それは、本当の舞台の姿だと、僕は思う。
そしてそれをやっているのが、大橋トリオ というアーティストだ。
彼は楽器演奏の才人にして、声も天性、作編曲もマエストロという、魔法使いのような人であり、まぁ書ききれないが、なおかつ人間臭さ、ユルさも持っている。
ここ何年か、この人の舞台に加わることができ、とても光栄、かつラッキーであった。
音楽をこんな面白いバランスで続けているアーティストは、本当に貴重です。
これからも、彼の活躍を信じ(るまでもない)、遠くからではあるが応援したいと思う。
ここからはご挨拶になります。
足掛け二年、しかし体感時間はあっという間だったツアーを無事終えることができました。
感染対策や振替公演、難しいやりくりを実行してくださったすべての関係者、メンバー、
そして、こういう状況にも関わらず、安全に気をつけてご覧くださったオーディエンスの皆さんに、改めて深く感謝申し上げます。
ここで、ある程度の時間をとって今後を考えたかったのですが、
そうもいかない事情もあり、結論を出すことにいたしました。
僕はこのツアーを持って、大橋トリオチームでの演奏活動から退きます。
このコロナ禍に対する僕の警戒レベルは、おそらく常人の倍以上。
陽性確認者が減る一方で死亡者が増加する? という不可解な状況で、情報が錯綜する中、これからがますます読みにくくなる。
そんな中、長距離を跨いでの生演奏活動を続けることに、東海地方在住の僕にはさまざまな面で無理があります。
本来ならば、ここは関東、関西どちらにも移動しやすい上、
また僕の観点では、情報過多の都会から距離を置きつつ創作・発信していく方が面白く、距離をさほどハンデには感じていないのですが、生演奏はリモートとは違います。
発信先がリモートでも、発信元は同じ場所にいる必要が(現在の技術ではまだ)あります。
また、特に ohashiTrio band のようなバンドマジックを生む為には、ディスタンスはあまりいつまでも有効には働かないことも、わかっています。
東京圏の音楽家たちがこの状況で頑張っているのも見聞きしているし、最近は実演その他も活発化しているようにも思える。それは、彼らの判断です。
彼らとして最大限の注意をし、仲間を大切にし、仕事と人生を大切にしている。もちろんガイドラインにも沿っています。
しかし、越境しながらこれをやるということは、僕一人の問題ではすまないことになります。もし感染を持ち込んだら。
そして医療はどこも、大変です。
音を作る、曲をつくる、詞を作る、それは引き続き、可能な限りやっていきます。
対外的にはともかく、自分の中では、それらは着実に育っています。
あるいは、単発のセッションはあるのかもしれない。
リモートのお仕事は歓迎します。
舞台の素晴らしさを改めて知った今、
それを自ら絶つことに虚脱感もあるのですが、
それも捉え方次第。The World is Mental, です。
もしかしたら何かで花が咲くかもしれない。
僕にはやりかけのことがあり、吸収したいことも、沢山ある。
そして、近年一番大きな、日本でも最高の音楽仕事であったチームを、
離れることにいたしました。
大橋くん、この縁を作ってくれた神谷くん、メンバー、
そしてここ5年余りの間に出会った
すべてのミュージシャン、スタッフ、トリオファンの皆さん、
本当にありがとうございました。
ごきげんよう。
ホールは屋根が高い。
奥が広い。
普段の部屋とこーんな違う世界。
味合わせてくれて
あんがとよ。
マスク越しでも
楽しんでくれれば
嬉しいな。
Thanks,
Ray