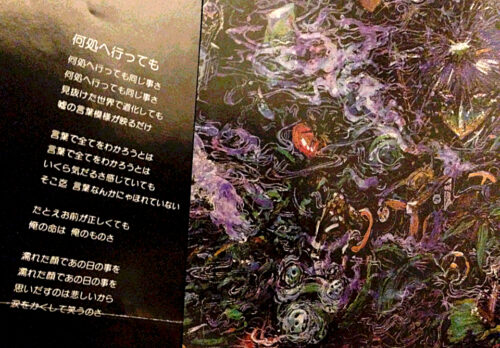11月はシークレットギグが数本。
レギュラーギグはない(予定)だが、その分つきつめたい事はいくつかある。
ふとFbassを見ると、変わったところに傷がつきまくっていた。

楽器に傷が付くのはたいがい必然性があってのこと。
なんでG弦側のピックアップの間が掘られているんだろうな、
そんな無意味な強烈なフィンガーピッキングしてたかな?
と考えてみたら、
サムピッキングのアンカーで中指の爪が掘ってるのだった。
うーん変わってる。
たぶんこんな傷を付けるのは自分だけだろうな。
Alain Caronにインタヴューしたとき、あれは12年前だったか、
東京ドーム近くのホテルのロビーで会った彼のFbassは結構ボロボロだったのを憶えている。
Alain Caronモデル=ピカピカ、みたいなイメージがあるけど、そんなんとんでもない。
使う楽器は、使われ倒しているのだ。
彼の音楽に影響されたとは言えないが、彼の考え方や指使いの方法論は凄く深かった。
彼は5フレット分を一つのポジションでカバーするのだ。
ただでさえスケールの長い6弦のFbassを。
ダブルベースなら3フレット(分)、エレキでも4フレットを守る人が多いのに。
こういう独自の理論ってやっぱり大事で、切り開いていかないと何も新しいものは生まれなかったりする。
Ray Brownの教則本を改めて見てもそう。だいたい教則本って、読者の予想を超えていることが多くて、
案外そこにこそ面白さがあったりする。予定調和とか兵隊的遵守じゃあかんのよね。
クリエイトだから。各自がそれぞれ、惑星のコア(=eARTh) になるための技だから。
そんなんはさておき、「王道」って大事だな、とも思ったりもする。
変に見えても王道とされているものや人には、やはりバシッと筋が通っている。
大木といおうか。
そんなことを、王道楽器のネックを触っていると、思ったりする。
ほんまやで。