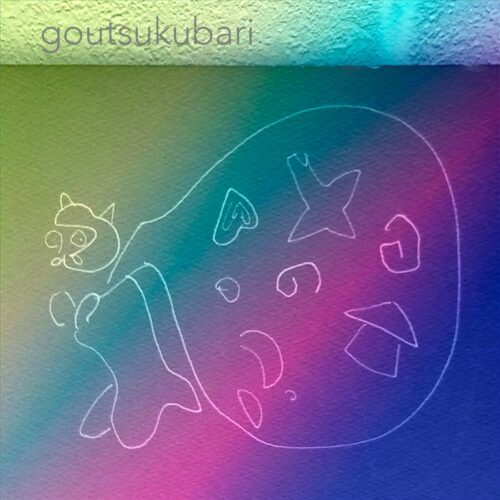…
チャーリー
ワッツ
…

っていう、リフレインの中の変な掛け声を聴いて、
当時ロックもろくに知らなかった僕はなんやねん、その人、と。
他にも、ゲイリーグリッターとか、マークボラン、デボラハリー、
あのこの嫌いな仲井戸麗市、なんでだこのやろう…
とか
清志郎さんのアドリブだったのかもしれないけど
この「エリーゼのために」というか、”BEAT POPS” と覚えてた RC サクセションの曲は
僕の中で特別だ。なぜなら、これが初めて人前でバンドで演奏した曲だから。
あの日はこの他、クリームの Sunshine of Your Love とか、モータウンみたいなベースラインのブルースとか、
スティービー の Isn’t She Lovely? の16ビートアレンジとか、やったっけ。どんちゃん?
先輩に混じって白いフレットレスベースを借りて、なぜかターコイズのジャンパー着て弾いたあの時は、ビデオ見返すと自分は人前に出てはいけなかった人だ(めぐりめぐって今もそうだ)が、
音はよかったし、先輩かっこよかったし、中でもずっとシャッフルビート弾いてた「エリーゼ」はその頃から歌詞がずっと、なんか、染みている。
…
Rolling Stones を好きな人は、まわりに結構いたけれども、自分はそうでもなく、
いつからこんなに好きになったのか、それはその後数年間、いろいろやってたバンドを全部やめてからだった。
京都はブルースマンやロッカーが多かったし、それに対する逆の壁、みたいなのも自分は感じてたから、
知ったかぶりするのもストレスで、正直、自分のペースで味わうのに時間がかかった。
でも、その昔にはじめて “Start Me Up” のビデオを観た時の衝撃はでかく
なんで、ロックバンドに公務員みたいなおじいさんが入ってるの? ちょーイイ人そうだし、ラクそーに叩いてるし 右手ピタッと止まってるし…
ボーカルのおっさん、ルパンと銭形が一緒になったみたいなキャラだし…
彼らこそがロックの典型なんだけど、それまで持ってたロックのイメージって
長髪とか、拳あげたりとか、なんか硬そうだったから、ぜんぜん軽やかでテキトーで、ひょうきんで、
あっこれやったらわかるわ、いやよーわからんけど、みたいな、のはあった。
でも当時はとにかく音楽全般、「ギター」っていう楽器に偏見っつーか抵抗があって、
エディだろうがウォーレンだろうがキースだろうが、フォークだろうが、あまり惹かれなかった。
単音楽器のベースかドラムか、あるいはシンセか、しか興味なかった。
身近でブルースギター弾いてる人はかっこいいと思ったよ、でも画面や写真のむこうからは。
で、なんとなくチャーリーワッツは好きだったけど、Stones 聴きまくりだしたのは、京都のスタジオでバイトやってた頃だ。
それからアメリカに数年行って、ジャズ学んでたにもかかわらず、しばらくはほぼ毎日 Between the Buttons と December’s Children を聴いてた。
というか、Charlie のドラムは、ジャズだった。あのフィールは、そこらの「ロック」(?)にありがちな四角いやつじゃない。楕円形で、しなやかで、伸び縮みして、いい加減で、繊細で、気持ちいい。
間違ってもフュージョンじゃないし、メトロノームなんかかけ離れている。でも、メトロノーム以上にビートをきめてくれる。
ビートルズとはまた違った、何百回でも聴けるスウィングとグルーヴがあった。
ビル・ワイマンのベースはほとんど注意して聴いてなかった。Live With Me とかのキースのベースは格別だけど。(今思えば Start Me Up のビルは壮絶かっこいい)
でも、ベースに耳貸さずとも最高に気持ちいい音楽が世の中にはたくさんあって、ストーンズはそれだった。
Cherry Oh Baby … Eric Donaldson のカバー、ワンドロップが途中、何回かひっくり返ってる。わざとっていうより…見失ったに違いない。
で、そのテイクがオッケーになっちゃったんだろう。
でもそんなんでも気持ちよく聴ける。この人おかしい。
チャーリーは、ビートのタイミングや鳴りもそうだけど、フィルでちょっと遅れたとこから「…ダダダダ」って追っかけて、しまいにはバンドを追い越してしまうみたいなとこがとにかく好きだった。
漫才してるみたいで。音楽聴くだけで、笑えてしまう。おもろい。歌詞の意味わからんでも、楽しい。
Cool, Calm & Collected のタイム感。深くて穴の開いた背広のポケット。エンディングの壊れたような加速。
….
もちろん、そのうち歌詞も気にしだしたけど、ミックの詞世界、自分に理解できるわけがない。あんな人生送ってないし。
(たまにわかるとなんだか嬉しい)
でも、それでも、大事にしたいと思う。宝物をくれた、人たち。
生で観れたのはマサチューセッツ州郊外のスタジアムと、東京ドーム。
前者はいつだったか… チケット高くて、$100ぐらいした。その頃アメリカは、日本よりずっと手頃にライヴ観れる国だったけど、彼らぐらいになると…というか、うまいこと買えんかったのか。
昼間のフットボールスタジアムで、前座はシェリル・クロウ。彼女はまぁまぁ有名だけどブレイクする前で、ごく前列にしか音も届かず、僕のスタンド席では誰も聴いてなかった。
Stones になったらどっかーん、スクリーンも映るし音も数倍だし、前座とメインの格差の凄さにも驚いたが。
そこいくと、数年後に観たドームは、正面とはいえあまり細部は覚えてない。スクリーンのアニメがいかがわしかったな…
近年も活動は気になってたけど、五反田に来たストーンズ展など観にいきつつ、聴くのは昔のレコード(音源)ばかりで、いい加減なファンだった。
長い闘病生活だったようで、想像できないぐらい辛かったのだろうけど、それでも、最後までジェントルだったんだろうな、とか、思えてしまう。
お疲れさま。
彼の域には、最初に思ってたところから 5mm も近づけなかったけど、この人が僕のこれまでの人生を、数倍楽しくしてくれたことは、間違いない。
ほんとにありがとう、チャーリー。
RIP, Mr. Watts –