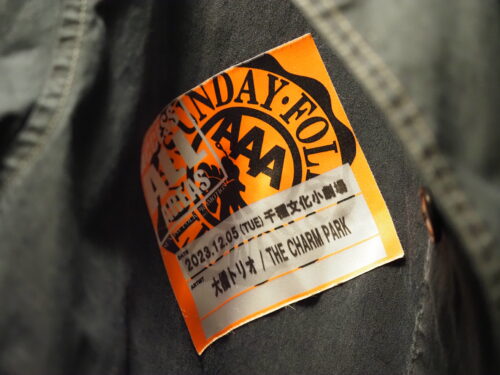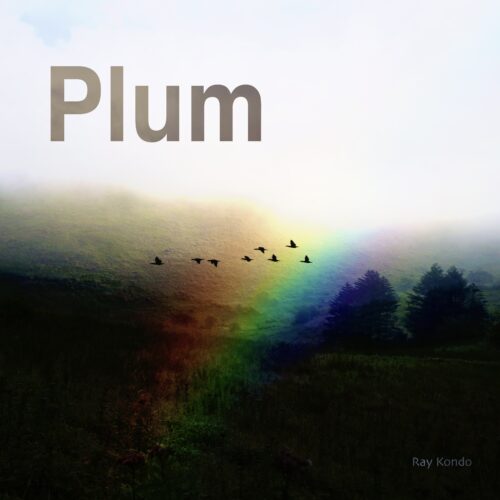最近、趣味ができた。
何かを忘れられること。忘れることができる何か。
なんでもかんでもいつも忘れっぱなしの気もするが
(こないだはベースを忘れて名古屋にいった。いや、それを盾に無茶振りを断ろうと思ったのだが、かわりにギターを渡されたというわけだ)
何を書こうとしていたかもう忘れてしまった。
没頭。これできること、趣味、あるよ。
そう、写真である。写真ほど、才能のあるなしが冷酷に出るものもないと思うが、
それでも、楽しいのである。
思うように撮れないこの5、6年を経て、今年はじめに思ったのは
もう、iPhone でええやん。
だった。Canon EOS M3 を持ってるのだが、これはもうなにしろピントが合わない。
オートフォーカス(AF)が遅いのは噂で聞いていて、それでもデザインと持ち心地とシャッターの音がよかったから、これに決めたのだが、もうなにしろ遅すぎる。
はっきりモニターに映っているものでも、延々と AF が合わず、いつまでたってもシャッターが切れない。
マニュアルフォーカス (MF) にすればとも思うが、ファインダーがないしどうもこれも合わんのだよ…
画質はとてもいいと思うのだが。
もう、10枚撮って1枚使えたらもうけもん、ぐらいで、ほとんど見放していたのだ。
そこいくと iPhone はすごい。どんなものにもたいがいピントが合うし(合わないわけが、ない)、live フォトなら後からフレームも選び放題。
画も結構きれいだし雰囲気もある。
そんなんで、カメラを持たずに iPhone だけで、やってきたのだ。たいがいは。
動画も M3 でやるのに懲りていたし、iPhone で十分。なんなら音もそのままでいいし。
ただグースネックのホルダーがどうも使いにくくて、いつも微妙に位置が決まらない。まぁまあ。これで十分やん。
でもどうしても。夜景や月は絶望的だし、望遠もツバメも難しい。
M3 に代わるものを探してはいるのだけど、よさそうなカメラは軒並み高価。
そんな中、必要に迫られて、サブスクでカメラを借りることにしたら、すっかりはまってしまった。
店の回し者ではないので、以降詳細は省くが、比較的安いランクの本体とレンズを、いろいろと交換して借りている。なんとなく、カメラの仕組みや得手不得手がわかってきた気がする。今頃。
キヤノンの EOS M6 はやはり M3 より全然速いし、ちゃんとピントも合う。でも入れ替えるつもりはない (M3 のほうがかわいい)。R7 は借りたの一瞬だけど、望遠動画もきれいに撮れた。R10 の AF は驚異的にすごかった。シャッター音がすごくチープで、ボディもうそみたいに軽くて、モノとしての魅力はなかったけど、道具としては十分すぎる。
ニコンは D750 を借りた。近くの写真屋さんが昔、秋祭りをそれで撮っていて、これいいよと勧めてくれてからなんとなく憧れていたのだけど、
ミラーレスに慣れてきてしまった自分には、大きくて重くて、左肩のダイヤルが回しにくくて、どうも合わなかった。
なぜか AF も精度が低かった。こんなもんだろうか? 発色や、はまったときの雰囲気は、すごいと思ったが。
枯葉を iPhone と D750 で撮ったら、その違いが凄まじい。




もちろん下が D750。
こんな、なにげない肌色の空の色合いも、好き。

こんな淡い、海辺とか。

だが、これとか D850 はプロじゃないと使いこなせんのだよ、と自分に言い聞かせている。
ニコンのミラーレス Z は、まだわからない。Zf はかっこいいけどなぁ。Z6 や 7 はどうも惹かれないし(高いし)、Z5 か Zf-c 借りて判断しようか…
ソニーはスペックも AF もすごそうだし、すごく売れてるみたいだけど、僕はどうも昔から Sony 製品と相性がよくない。音の機材でも、たくさん買ったけど…なのでどうも使いたいと思わない。借りてみたらやっぱこれええやん、とか、これを知らずして今のカメラを語るな、となるかもしれないけど。
オリンパス、今の所、一番合ってるのはこれかと思う。もうブランドは OM SYSTEMS になってるけど、OM-D E-M5 がすごくいい。買うなら最後の Olympus ロゴの OM-1 が欲しい…と思いながら、大丈夫かなぁと二の足を踏んでいる。

E-M5 は一度返したけどまた別のレンズと借りてて、やっぱりいいなと思っている。絶妙にクラシカルデザインで、裏にグリップが少しだけあって、よく右手にひっかかる。また、シャッターボタンがおさまったダイヤルが、絶妙に使いやすい。このへんは OM-1 と違うんだよな…
撮る対象は人より湖岸の鳥や月や、自分はなにげに望遠レンズが好きらしく、フルサイズだとかなり大変なことになりそうだ。マイクロフォーサーズや APS-C なら、コンパクトに望遠セットが組める。これ、かなり重要かもしれない。
一方で暗い景色が基本的に好きで、なんとかこの陰影を写したいといつも思っているので、そこは画素数を控えたフルサイズなどがいいんだろうけど… 完全に矛盾じゃないか。

まだ借りてないけど、ルミックスはどうなんだろう。S5 や S5mkIIx は使いたいと思う。初代の G9 Pro も触っとくべきかもしれない。AF は Canon や Sony にかなわないらしいが、それでも EOS M3 よりは何倍かいいんでしょ?
あとは SIGMA ですね…
機材自体で面白がるのは、男子の永遠の病気だろうな。
また、もっと写真自体について記します。たぶん