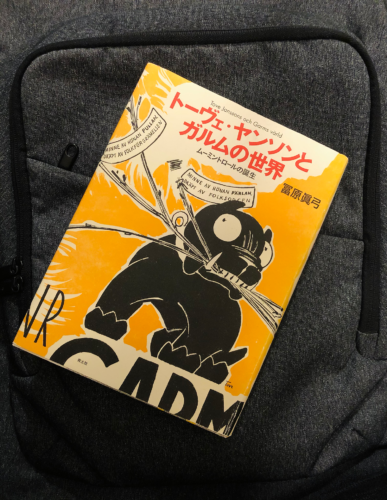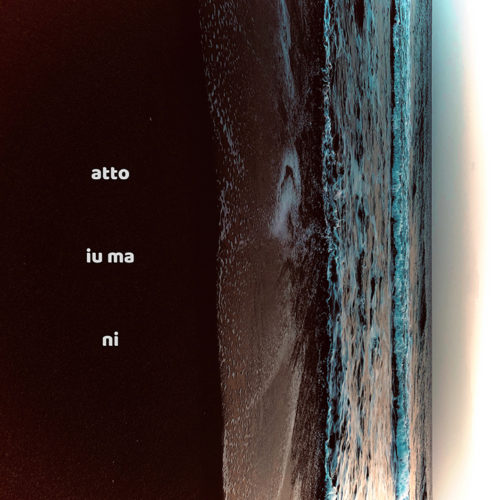空き時間に部屋を整理。
あの禁音部屋…とは違うが、ここはとても小さい。
手始めに、仕事相手からずっと借りていたモニターをお返しし、
自前を買う。モニターといってもディスプレイの方。
机が渋滞し、鍵盤も窮屈なのでトレイの自作を思うも、
角置き専用の特殊な机で工作が難しい。ふと、机の下に鍵盤を配置できたとしても低すぎることがわかり、潔く諦める。
ピアノの白鍵の表面は、床から75cm。机にキーボードを置いても75cm。同じ方がいい。
モニターもトレイも何年も悩んでたが、さっさと決めた方がよい。
マイペースに行きたいなら、余計に時間が大切だ。
代わりにモニターアームを買う。これなら机を広く使えるし、
首や肩の負担も減る。
このモニターは、USB-C 接続だけで MacBook に給電もできるので、とても助かる。
言うことなし、と言いたいが、完璧ではなかった。
MacBook Pro、16インチモデルは、外部ディスプレイに繋ぐと突然発熱し、ファンがぶん回る。
煩くてしょうがないから、録音の時には本体のディスプレイしか使わない。すると嘘のように静かになる。
これは僕だけじゃなく発売当時からずっと言われてることだし、先日 maba くんも言ってたから、やっぱ不具合なんだろう。
Apple が認めるとは思わないけれども、フラッグシップモデルでこれって、ちょっとないよな。
ファームウェアで解決だろうという話があったけど、その後何も聞かない。
たぶん M1 Mac や Big Sur を優先して、近過去はすぐに切り捨てなのだと思う。
レジェンドは大切に、レガシーはないがしろ。何かの縮図だ。*
と、文句を書きつつも、これはなんとかなる。
ところがもうひとつ、USB-C の同時給電、やはり落とし穴があった。
Audio I/O からスピーカーで鳴らすと、ノイズの嵐。なぜか、ヘッドフォンではノイズレス。
電源分けてるのに、グラウンドループか。
試しにディスプレイの電源を落とすと、ノイズは消える。完全に USB PD のせいだ。
昔から、新幹線で iPhone を充電しながら音楽を聴くとノイズだらけになったりしてたから、
だいたい予想はしていたのだが、このモニターは何の対策もできていないようだ。
一番信頼していた、日本製。
仕方ないので、巨大な白いアダプターを復活させる。ノイズは消えた。
いつまでたっても、何かしら欠点があるシステム。でもこれでやっていこう。
* MacBook Pro の熱暴走については このサイト が一番はっきりしてる。
排熱設計の欠陥。だから eGPU を買えば解決って、完全におかしなスパイラル。
リコールにするべき。